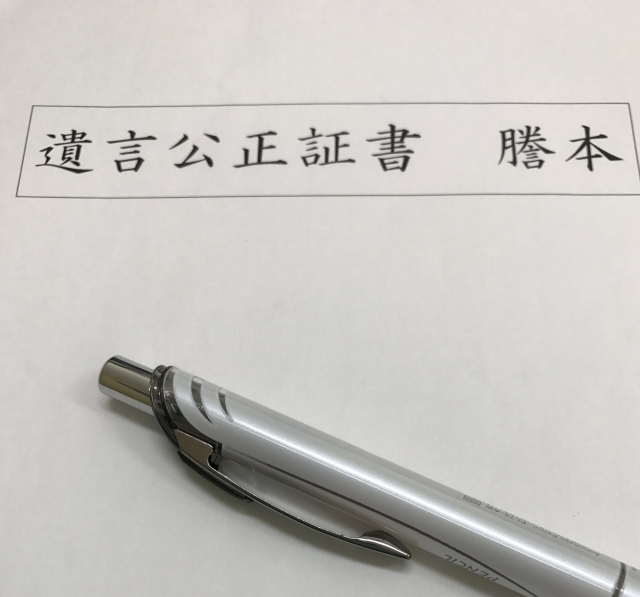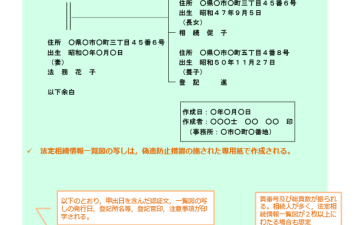近年、遺言書を作成される方が増えています。
日本公証人連合会の統計によると、平成29年の遺言公正証書の作成件数は11万191件で、平成19年の7万4160件から比べて、この10年間で約1.5倍に増えています。
遺言に関する本が多数出版され、世間一般にも遺言の存在が広く浸透していると思います。
しかし、遺言書を作成する方は、国民全体からするとまだまだ少数派だと言えます。
一定の年齢を超えると記憶力や判断力は徐々に低下していくものですし、急速な少子高齢化によって社会環境が大きく変化している中で、元気なうちに遺言書を作成しておくことは大切なことだと思います。
備えあれば患いなしということで、今回は、遺言書を作成しておくべきケースをいつくか取り上げてみたいと思います。
なお、遺言以外の方法(例えば、信託や死後事務委任契約等)を用いたり、組み合わせたりして利用した方が良い場合もありますのでご留意ください。
1.夫婦に子供がいないケース
例えば、被相続人が夫で、相続人が妻、夫の弟、夫の妹だったとします。
この場合、もし遺言がなければ、妻、夫の弟、夫の妹の3人で遺産分割協議をしなければならず、分割協議がうまくまとまるかどうか分からないといった懸念や、うまくまとまったとしても遺産分割協議書に実印を押して印鑑証明書を提出してもらわないとならないなど、残された配偶者に手続的・心理的な負担をかけることになります。したがって、このようなケースでは、遺言書を作成しておくべきといえます。
夫婦が協力して一緒に築き上げてきた財産であれば、夫は「全ての財産を妻に相続させる」とし、妻は「全ての財産を夫に相続させる」とする内容の遺言書を夫婦相互に作成しておけば、「配偶者が一人になっても安心して暮らしていけるようにしたい」という願いをある程度形にできるのではないでしょうか。
留意点としては、共同遺言は禁止されているので、夫婦別々に遺言書を作成する必要があることです。また、上記のような「全ての財産を配偶者に相続させる」旨の遺言を相互に作成した場合は、一方が死亡したときは、残された側が作成した遺言書(「全ての財産を配偶者に相続させる」とする条項部分)は、相手方が死亡した時点で効力を失うことになります。
なお、兄弟姉妹に遺留分は認められていないので、上記の例でいうと、妻が夫の兄弟姉妹から遺留分減殺請求権を行使されることはありません。
次に、上記の相続関係はそのままに、夫の財産に親から承継した財産が含まれているケースを考えてみます。例として、住んでいる土地が先祖伝来の土地だったとします。
先ほどと同じように、夫が「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言書を作成した場合を考えてみます。このような遺言をして先に夫が死亡した場合は、夫の財産は全て妻が取得することになります。
それでは、その後妻も死亡した場合は、どうなるのでしょうか。
そのときは、妻の相続人(妻側の父母又は兄弟姉妹等)に財産が移転することになります。
これでは夫の兄弟姉妹としては、先祖伝来の土地が妻の相続人のものになってしまい、納得がいかないことでしょう。遺言者である夫がそれで良しと考えるならそれでも良いのですが、夫としても先祖伝来の土地を妻の相続人に引き継いでもらいたいと思わないのであれば、さらに先のことも考えて遺言書を作成しなければなりません。
後継ぎ遺贈の問題
例えば、夫が「先祖伝来の土地は妻に相続させ、妻が死亡した後は、先祖伝来の土地を弟に相続させる」旨の遺言書を作成したとします。これは、いわゆる後継ぎ遺贈といわれるもので、通説では無効とされています。ただし、昭和58年3月18日最高裁判例は、後継ぎ遺贈と解される条項のほかに多数の条項からなる遺言書が作成された事案において、遺言の解釈について以下の基準を示し、原審判を破棄し差し戻しました。
遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である。
後継ぎ遺贈については、その有効性が確定しておらず、むしろ否定的な見解のほうが多いので、今のところは避けたほうが無難です。
後継ぎ遺贈以外の方法
後継ぎ遺贈以外の方法としては、遺言者が第一受遺者に遺贈する旨の遺言と第一次受遺者が第二受遺者に遺贈する旨の遺言を併用する方法が考えられます。上記の例でいうと、夫は「先祖伝来の土地を妻に相続させる」とし、妻は「(夫の)先祖伝来の土地を夫の弟に遺贈する」とする旨の遺言書を作成するやり方です。ただし、この方法はよほどの信頼関係が構築されている状況が必要であると思います。
もう一つの方法は、後継ぎ遺贈型受益者連続信託を利用する方法です。後継ぎ遺贈型受益者連続信託については、今回は割愛します。
2.行方不明の相続人がいるケース
行方不明の相続人がいる場合、有効な遺産分割協議を行うためには、行方不明者のために不在者財産管理人の選任を申立てなければなりません。また、遺産分割協議は、不在者財産管理人の権限外行為に当たるため、裁判所から権限外行為の許可を得ることも必要になります。
相続開始後の煩雑な裁判手続を避けるためには、遺言書を作成しておくべきといえます。
3.相続人が誰もいないケース
相続人が誰もいない場合、遺産はどうなるのでしょうか。
わずかな遺産しかない場合は別として、不動産や預貯金等の一定の遺産がある場合は、利害関係人又は検察官の申立てにより相続財産管理人が選任されることになります。
相続財産管理人は相続人捜査の公告を行い、期間内に相続人である権利を主張する者が現れなかったときは、特別縁故者への財産分与、それもなかったときは、残った財産は国庫に帰属することになります。
したがって、相続人が誰もいないケースも、お世話になった人に遺贈するとか公益目的を達成することのできる団体に寄付する等の遺言をしておくべきケースといえます。
どの団体に寄付したいか決まっていない場合は、具体的な選定基準を決めて、遺言執行者に選定を委ねるといった遺言もできます。ただし、遺言代理禁止が原則ですので、選定基準はかなり細かく決める必要があります。
4.財産を特別多く与えたい相続人がいるケース
財産を特別多く与えたい相続人がいる場合も、遺言書を作成しておくべきケースです。
この場合、相続人が揉めないように遺言の文言には気を付けないといけないですが、特に留意しなければならないのは遺留分の問題です。
遺留分は、一定の相続人に取得することが法律上保障されている遺産の割合です。
遺留分を侵害する遺言が当然無効になるわけではありませんが、遺言書を作成するにあたっては遺留分について検討する必要があります。
遺留分を侵害しないような遺言書ができればそれにこしたことはないのですが、「全財産を特定の相続人に与える」といった旨の遺言の場合は、どうしても遺留分の問題が避けられません。
全財産を特定の相続人に与える理由がその他の相続人に対し十分な贈与等を行っているためである場合は、特別受益としてその贈与等の事実関係をなるべく詳しくに遺言書に書いたり、特定の相続人に事業を承継させるためである場合は、事業活動に影響を及ぼさないように遺留分減殺請求の順序を指定したりするなどの対策が必要です。
なお、遺留分を相続開始前に放棄するには、裁判所の許可が必要です。
今回は、遺言書を作成しておいたほうが良いケースをいくつか取り上げてみました。